
Kindle電子書籍リーダー
ご注文は下記をクリック🔽
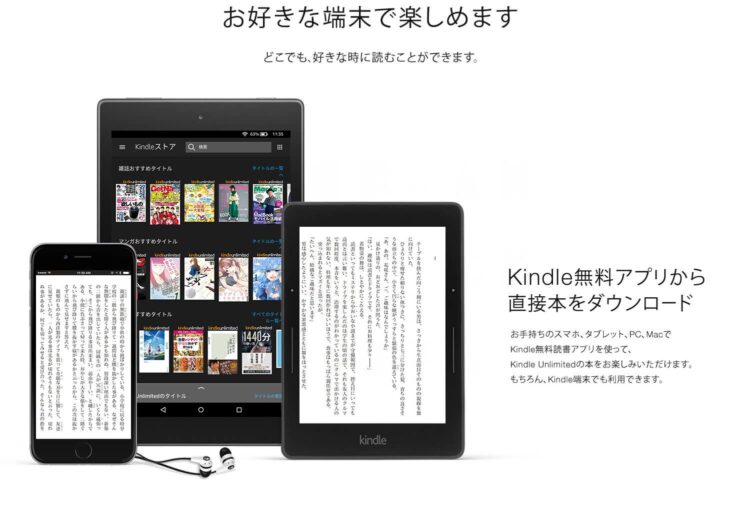
Amazon
こんにちはブログ管理者アッキーです。訪問ありがとうございます\(^o^)/
今回は、前回記事のしなの鉄道沿線ランニングで、ぶらりと立ち寄った歴史的建造物など、紹介しきれなかった観光名所を、画像を交えて紹介します。前回記事と画像やコメントが重複するところがありますが、少し情報を増やして紹介していきます。
過去記事の鉄道ランニングの区間は小諸駅ー大屋駅でしたが、帰りはしなの鉄道に乗って戻りました。人気のしなの鉄道の沿線には、真田氏や武田信玄が活躍したお城や、重要伝統的建造物保存地がある宿場町など見どころ満載です。鉄道ランニングでは大屋駅まででしたが、その先上田駅にも行って、上田城を見学して来ましたのでその旅行記を報告します。よろしければお読みください。
しなの鉄道ぶらり沿線ランニングの過去記事です。
上田市は長野県の中でも長野市、松本市に次ぐ規模の市で、人口は約15万人。上田駅前は人通りも多く、商業ビルが立ち並び賑やか。上田市は真田氏三代の郷として知られ、真田氏が築いた上田城がある城下町。

▼上田駅。上田城はここから歩いて15分ほどの場所にある。

上田駅はしなの鉄道や長野新幹線、別所温泉とを結ぶ上田電鉄別所線が乗り入れている駅である。

千曲川にかかる別所線の橋梁。この先は上田駅。

反対側は城下駅方面に延びる線路。

菅平の山と千曲川と赤い橋のコントラストが美しい。

堤防に踏切りがあったので、別所線を撮影してみましたのでご覧ください。

上田城跡公園にある上田城は1583年に真田昌幸によって築城され、築城当初は「尼ヶ淵城」と呼ばれることもあった。上田城の合戦では徳川軍を2度も退けた実績があり、真田氏・仙石氏・松平氏と12代にわたって守られてきた名誉あるお城だ。

関ヶ原の合戦後上田城主は真田信之となった。真田氏は平安時代から長野県の中心的な存在であった、滋野氏・海野氏の一族で真田幸隆が武田信玄に仕えた頃から存在感を現わす。現在残っているお城は、仙石忠政によって江戸時代初期に再建築された。

西櫓は1626年頃仙石氏によって建てられた武器庫。江戸時代から残る上田城唯一の建物。

真田幸村像を背景に見た西櫓。

西櫓の格子窓は、外の様子を伺う目的で作られ、棒で突き上げて素早く開けられる戸がついた武者窓。

この辺りに本丸があった場所のようだ。上田城跡公園には1,000本の桜が植栽されており、桜が咲き誇るシーズンには、上田城千本祭りが開催され多くの市民や観光客で賑わう。

櫓の見学も可能だ。

東虎口櫓門右側の石垣にある、高さ約2.5m幅3mの大石は、真田昌幸が上田城築城の際に積み上げた。昌幸の子、真田信之が松代城移封になり家宝として持っていこうとしたが、全く動かなかったという伝説がある。

真田神社。御祭神は真田氏、仙石氏、松平氏という歴代の上田城主を祀っている。もともとは松平家の御先祖をお祀りする御宮であり、松平神社と称していた。

真田氏は2度の合戦があったにもかかわらず、負けなかった不夜城と知られ、落ちない城として受験生に人気。

絵馬の回廊。境内には願いが書かれているたくさんの絵馬が吊るされている。高校受験や大学受験の他国家試験の合格祈願に全国から訪れる。

上田市立博物館は上田の歴史を知ることができる博物館だ。歴史資料や民俗資料、特徴的な収蔵品、歴代上田城主の鎧や兜などの国指定の文化財66点が展示されている。

上田城跡公園から見下ろす上田駅方面の風景。上田城の情報はこちらのサイトから🔽
