2025年11月21日更新。
この記事は最新の情報をお届けするため定期的に更新しています。

宿場町や城下町の町並みが
わかり風情が感じられる本
ご注文は下記をクリック🔽
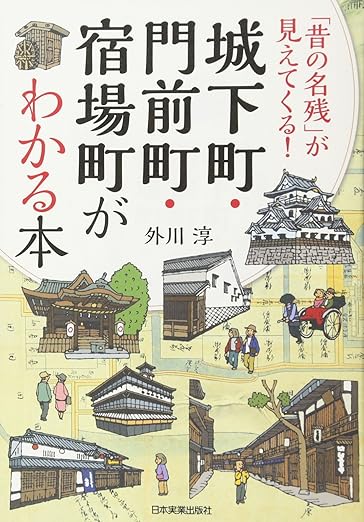
Amazon
こんにちはブログ管理者アッキーです。訪問ありがとうございます\(^o^)/
今回は江戸時代の幹線道路、五街道のひとつ中山道にある宿場町の特集です。先日観光で訪れた馬籠宿の画像を交えて紹介します。
目 次
中山道の宿場町を訪ねる江戸時代にタイムスリップ
中山道は江戸から、上野・信濃・木曽・美濃・近江を経て京三条大橋とを結ぶ、約534kmの街道である。中山道には69の宿場町があり、街道の整備により集落ができ、旅人の宿泊所や、宿泊所を取り次ぐ業務を行う本陣や旅籠などの問屋場があった。奈良井宿や中津川宿、馬籠宿、妻籠宿など今も江戸時代の面影を残し、歴史を感じる見どころや魅力がある宿場町が多数あります。

最近筆者は宿場町に訪れる機会があり、海野宿と馬籠宿を見学してきました。宿場町というのはかつて商人や旅人で栄えた町で、当時のまま建物を保存し、ノスタルジックな町並みが過去を再現していることに興味を持ち、関心を持つようになりました。できれば69全ての宿場町巡りをしたいと思っていますが、534㌔もある距離だから短期間で巡るのは難しいので、これから少しずつ訪ねて、ブログで伝えて行ければいいかと思っています。
2つの宿場町の観光レポートの前に、まず中山道の宿場町で、江戸風情のある街並みが残る名所を調べてみました。長野県と岐阜県にある宿場町を紹介します。
江戸時代の景観 現存する建物おすすめ宿場町
1.難所続きの信濃路は宿場町として栄えた
小田井宿は江戸から21番目の、長野県の御代田町南西部にある宿場町。中山道と北国街道の分岐点にあり大名が追分で宿を取り、姫君は小田井宿で宿を取ることから「姫の宿」とも呼ばれる。間口が広くゆったりとした宿場だったということだ。
▼小田井宿。徳川家に嫁いだ皇女和宮の嫁入り行列を再現する、小田井宿まつりは毎年8月に開催される。

望月宿は江戸から25番目の宿場。長野県佐久市望月にある、この地を仕切っていた望月氏の性や、蓼科山裾野の望月牧から望月の名がついたと伝えられている。1765年に建てられた、望月宿にある問屋を兼ねた旅籠大和屋は国の重要文化財に指定されている。
▼望月宿。中秋の名月に信濃から馬が送られてくる、その代表格であった場所が望月の名がついたとも言われている。

長久保宿は江戸から27番目の宿場町。長野県小県郡長和町にある、中山道難所の和田峠と笠取峠の間にあり、北国街道の分岐点にあったことから、最盛期には50軒もの旅籠があり、信濃の宿場町有数の規模を誇る宿場だった。明治初期に旅籠として建てられた濱家は、2階の部屋を広くする工夫を凝らした出桁造りであったが、旅籠として開業することはなく、住居として使用された。その後長久保宿歴史資料館として展示の場として公開されている。
▼長久保宿。当初現在場所より西側依田川沿いにあったが、大洪水により流失したため1631年に現在の高台に移った。

和田宿は江戸から28番目の宿場町。長野県小県郡長和町にある標高820mの高地にある静かな佇まいの宿場。長久保宿の次にあたる和田宿は背後に難所和田峠があり、隣の下諏訪宿まで22kmという長丁場だったため、多くの旅人が宿場として利用し栄えた。
▼和田宿。中山道の最高地点にあり、最大の難所と言われる和田峠を控えた宿場として多くの人旅人が利用した。

和田宿本陣は中山道の宿場の中でも数少ない遺構を残す建造物で、国指定の史跡である。本陣建物は大名などの要人にあてられる座敷棟と、所有者が生活する居住棟に分けられる。

下諏訪宿は江戸から29番目の和田宿の次にある、長野県諏訪郡諏訪町の中心部にある宿場町。難所であった和田峠の西の入り口として諏訪大社の下社の、社寺が周辺にある、門前町として栄えた。
▼下諏訪宿。中山道と甲州街道が交わる要所として栄えた。

本山宿は江戸から32番目の宿場町。木曽の入り口、松本平の出口として繁栄した、長野県塩尻にある宿場。出格子の2階建ての家が立ち並び、当時の面影が残る蕎麦切り発祥の地として知られている。
▼本山宿。明治時代の建築で平入り出桁造り、千本格子の2階部屋など当時の町並みが多く残っている。

2.自然豊かな山深い谷の街道木曽路
奈良井宿は江戸から34番目の宿場町。長野県塩尻市にある宿場。木曽11宿の中では最も標高が高く、難所の鳥居峠を控え多くの旅人で栄え、奈良井千軒と親しまれた。花の観光地づくり大賞・美しい日本の歴史的風土百選など、数々の賞を受賞してきたこの宿場町は、連続テレビ小説の「おひさま」の舞台にもなった美を、身近に感じることができる地として、国内外から多くの人が訪れる。
▼奈良井宿。400年の歴史ある宿場町は、重要伝統的建造物群保存地区に指定されている。

妻籠宿は中津川市の隣長野県南木曽町にある。江戸から42番目の宿場町。全国で初めて古い町並みを保存した宿場町。木曽の宿場の中でも最も保存状態が良く、国の重要伝統建造物群保存地区に指定されている。約800mの通りには、飲食店や土産物店に変わった古い建物があり歴史を感じながら散策できる。
▼妻籠宿。妻籠の人たちは町並みを守るため売らない、貸さない、壊さないという原則をつくり保存している。

3.険しい坂道や三大難所太田の渡しを抜け美濃路へ
落合宿は江戸から44番目の宿場町。木曽路の玄関口落合宿は、岐阜県中津川市にあり、木曽路の厳しい難所を控える旅人を迎えていた。落合宿本陣は、岐阜17宿のうち、唯一当時の姿を留めている。本陣は、上級官人や大名など重要な人物を泊める施設として宿場において重要な役割果たした国指定の史跡。
▼落合宿。映画十三人の刺客で決戦地の舞台にもなった宿場町。

中津川宿は江戸から45番目の宿場町。岐阜県中津川市にある、中山道と飛騨街道が交差し、日本各地から人々が行き交う交通・商業の重要な拠点だった商業の街として栄え、その面影は裕福な家で見られる、屋根の上にある「うだつ」からもうかがえる。
▼中津川宿。美濃地方随一の商業の町として栄えた町並みにはうだつが残る。

太田宿は江戸から51番目の宿場町。岐阜県美濃加茂市にある。中山道の三大難所のひとつに数えられた木曽のかけはし太田の渡しがあり、飛騨街道と郡上街道の分岐点であったことから繁栄した宿場町。
▼太田宿。旧太田本陣林家住宅や、旧太田宿本陣門など国の指定文化財や市の指定文化財など当時の面影を残す建物が多数ある。

▼旧太田宿本陣門。1861年仁孝天皇の皇女和宮が、14代将軍徳川家茂に嫁ぐために下向した際に新築された門。現在本陣の建造物は残っていないが、旧本陣を知る遺構として正門を現存している。
